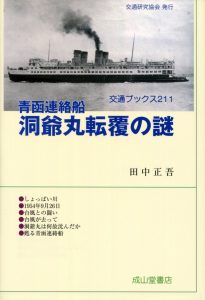友愛労働歴史館は渋沢史料館の井上潤館長をお招きし、11月6日(水)14時から講演会「渋沢栄一と鈴木文治」(友愛会館8階・友愛労働歴史館研修室)を開催いたします。これは当歴史館が開催中の企画展「協調会結成100年―渋沢栄一と鈴木文治・友愛会―」(2019.7.4~12.24)に連動したもので、誰でも参加できる講演会(参加費無料)です。
また、講演会終了後、当館解説員による企画展「渋沢栄一と鈴木文治」(友愛会館8階)のミニ見学会(20分程)を実施いたします。ミニ見学会では企画展示室をご案内するとともに、協調会を主導した日本近代資本主義の父・渋沢栄一と、友愛会を創立した日本労働運動の父・鈴木文治の出会いと別れ、協調会・渋沢栄一と友愛会・鈴木文治が共有した「人格の尊重」などについて解説いたします。
なお、講演会・ミニ見学会ともEメールyuairodorekishikan@rodokaikan.orgで、友愛労働歴史館宛に参加申し込みをお願いいたします。これは資料などの事前準備の関係です。